お役立ち情報 ラーメンを深く楽しもう
ラーメンのひみつ
たった一つの丼の中に麺、スープ、具がフルコースとなって完成する「ラーメン」
最高にうまいラーメンは、この3つの要素が絶妙にマッチしていると言って過言では、ないでしょう。
ここでは、この3要素の秘密についてお見せします。
具のひみつ
たまご

玉子は、栄養学的には「完全食品」と呼ばれているように人間の体に必要なたんぱく質やカルシウム、鉄分などの栄養素をまんべんなく含んだすぐれた食品です。たった1種類でこれほど栄養面でバランスがとれた食品は、玉子を除くと、牛乳以外には見当たらないとさえ言われるほどです。
ラーメンにおいては、とくに不足するたんぱく質を補う効果があり、なおかつ淡白な甘さから、スープで塩辛くなった口の中を落ち着かせてもくれます。
玉子はこのようにラーメンの具として優れたものですが最近その食べ方として脚光を浴びているのが「煮玉子」です。
札幌では、まだ少数派ですがトッピングとしてのせる店、カウンターにおいてセルフサービスにする店と「煮玉子」をセールスポイントとするお店は、着実に増えています。
このブームのきっかけは、もともと、台湾料理の「魯蛋(ロータン)」をラーメンに浮かべたものが始まりと言われ東京荻窪から全国に広がって行ったようです。
煮玉子の作り方は、カラをむいたゆで玉子をしょうゆたれに漬け込む店、あるいは、煮こんだ後、味がしみこむように冷蔵庫でさらに数時間寝かせるお店など様々です。
いずれにせよこの「煮玉子」注目の具として今後も目が離せない存在と言えるでしょう。
可食部100gあたりの栄養価。(四訂食品成分表より)
| 栄養成分 | 単位 | 鶏卵 | 豚肉 | マグロ | 牛乳 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 12.3 | 17.0 | 28.3 | 2.9 |
| 脂質 | g | 11.2 | 20.5 | 1.4 | 3.2 |
| 糖質 | g | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 4.5 |
| カルシウム | mg | 55 | 5 | 5 | 100 |
| リン | mg | 200 | 147 | 280 | 90 |
| ナトリウム | mg | 130 | 43 | 50 | 50 |
| 鉄 | mg | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 |
| ビタミンA | IU | 640 | 23 | 20 | 110 |
| ビタミンB2 | mg | 0.48 | 0.23 | 0.09 | 0.15 |
もやし
伝統的札幌味噌ラーメンの具の代名詞とも言える「モヤシ」。 具として初めて「モヤシ」を使うことを考案したのが味噌ラーメンの生みの親、大宮守人氏です。昭和20年代前半、札幌ラーメンの具といえば、メンマにネギ、チャーシュー、なるとといったものでした。いずれの具もラーメンの上に載せるだけでよく、麺をゆでている間の手持ちぶさたが、大宮氏には、どうしても気になった。麺がゆであがるまでの時間で何かできないかと考えて思いついたのが中華料理でおこなうフライパンさばきでした。 フライパンで野菜を炒める姿は、なかなか威勢がよくお客様へのちょっとした見せ物にもなるしそれをラーメンに載せれば、栄養にもなるし客も喜ぶに違いない。
では、何を炒めたら良いのか…
タマネギは、ベストでしたがコストが掛かる上、季節によって品質が変わるという問題があったため考えあぐねた末、思いついたのが当時あまり食べられず、しかも安価であった「モヤシ」でした。また「モヤシ」の食感に負けないように札幌ラーメンの麺もその後太くコシのあるものが使われるようになりました。
現在、日本で一般的に使われる「モヤシ」は、インド原産の「ブラックマッペ」という種類でビルマやタイ、中国から輸入したものが使われています。この「モヤシ」は、甘みこくが優れた品種ですが太くならず見栄えが良くないという欠点もありましたが現在では、低温長期熟成の製造方法で太い「モヤシ」を作ることができるようになりました。
なお「もやし」は、植物の種子が一番活発に成長している時期を食べるため栄養価も高く、ダイエットやボケ防止効果もあると言われています。またラーメンの具として使用する場合は、ニンニクの匂いをおさえるという効果もあります。

長期低温熟成により製造された「ブラックマッペモヤシ」。美味しいモヤシを作るポイントは「水」。この工場では、支笏湖の地下状流水を使用しています。
写真提供 ミキ食品株式会社
なると

かつては、メンマ、チャシューと並んでラーメンの具の御三家だった「なると」。最近では、「なると」を入れないラーメンが主流になってしまい寂しいかぎりです。 練り製品であるなると巻は、れっきとしたかまぼこの仲間で純粋な日本生まれの食品です。その歴史は古く、1846年発行の「こんにゃく百珍」という書物に記述が確認されています。
もともとは、瀬戸内海から捕れた白身の魚を原料に、食紅を使って赤く染めたすり身を渦巻き状に巻いてゆでて作ったのが始まりとされ切り口が鳴門海峡のうずしおに似ていることから「なると」と呼ばれるようになったようです。 現在、なると巻の最大の生産地は静岡県焼津市、国内で消費されるなると巻の約9割がここで作られています。
焼津でなると巻の製造が始まったのは、大正末期のこと。主にそばの具として使われていたのが一般化したのは、ラーメンが普及した昭和初期からでした。 以来、なると巻の需要は、ラーメンの普及とともに増え続け、さらに「なると巻成形機」の開発で大量生産に結びついていきました。
ラーメンにおける「なると」の最大の効果は、やはり視覚的要素が大きいのではないかと思われます。目に楽しく食べておいしい「なると」は、ラーメンに味と色のアクセントを添えていると言えるのではないでしょうか?
ねぎ

根深ネギの素材をふんだん生かしたネギ味噌ラーメンは、札幌ラーメンの隠れた人気メニューのひとつだ。
チャシュー、メンマとならんでラーメンには、欠かせない具のひとつネギ。流通経路の発達により全国的に同じ品種の野菜が広くでまわるようになる中で、ネギは、今なお地域による独自性を保つ数少ない野菜のひとつです。
ラーメンの上にのっているネギは、関西や九州では、青ネギと呼ばれる株分れしやすい葉ネギがよく使われます。代表的なのが京都の九条ネギや博多の万能ネギです。甘くて香り高い味わいは、味も香りも濃厚なスープにぴったりマッチします。一方、関東では、白ネギと呼ばれる葉身が比較的硬く、白い部分を食べる根深ネギがよく使われます。代表的なのが埼玉の深谷ネギ、ネギ特有のピリッとした味わいの中にも甘みが広がり、シンプルな醤油ラーメンによく合います。
ネギは、刻んだ瞬間からその香りが飛び始め、時間がたつとその香りが薄れてしまうため、その本来の香りを楽しむためには、麺がゆであがる直前にネギを刻んで、たれと一緒にどんぶりの中に入れ、その上からスープを注ぐのが理想といえます。ただラーメン屋さんでここまでこだわるお店は、少ないかもしれません。
ネギの効能としては、辛味の成分であるアリシン(硫化アリルの一種)が、胃腸を刺激し、消化液の分泌を促し、食欲を増進させる効果があります。またビタミンB1の吸収を促進する働きもあり疲労回復の効果もあるといわれています。
ネギの種類と特徴
| 品種 | 銘柄 | 特徴 |
|---|---|---|
| 千住ネギ群 | 深谷ネギ | 埼玉県深谷市周辺で作られる茎が太く柔らかいネギ。 |
| 金長 | 病気に強く、作りやすい上に見た目もよいため、最近では、根深ネギのほとんどがこの種類。 | |
| 加賀ネギ群 | 下仁田ネギ | 群馬県下仁田町の特産品。太くずんぐりした独特な形。甘みがあり鍋などによく使われる。 |
| 岩槻ネギ | 埼玉県岩槻市で栽培されるが、関東では珍しい葉ネギ。 | |
| 越津ネギ | 愛知県津島市で栽培される。 | |
| 九条ネギ群 | 九条ネギ | 全国的に作られている京都が発祥の葉ネギ。太ネギ群と細ネギ群がある。 |
| 万能ネギ | 九条ネギの栽培法を改良した博多発祥のネギ。 | |
| その他 | あさつき | ネギの近縁種、辛み、香りが柔らかいのが特徴 |
| わけぎ | 独特の香りは、ネギに似ているが植物学上は、別種 |
ほうれん草

イラン(旧ペルシア)から伝わったといわれる野菜・ほうれん草。日本においては、1631年の「多識篇(たしきへん)」という文献のなかで「唐菜(からな)」という名で紹介されたのが最初で、16世紀頃中国から伝えられたものと記述されています。
ほうれん草には、根が鮮紅色で、葉が細く、先がとがって切れこみが深い、秋に種をまく東洋種と葉が丸く肉厚のある春に種をまく西洋種があります。近年は、西洋種の葉肉の厚さと東洋種の味のよさなどそれぞれの利点を生かした交配種が主流で、1年中出回るようになりました。
ほうれん草は、ラーメンの具として一般的とは言えないものの、栄養学的には大変優れた野菜で、ビタミンA、B1、B2、C、が豊富に含まれるほか、鉄分も多く、体内で血を作る効果が大きいため貧血性の人にとっても予防効果のある良い食べ物です。また見た目の彩りもよく、あっさり系の醤油味には、スープの味をジャマしない、ぴったりの具と言えます。野菜が不足しがちなラーメンにおいて、是非とも具として加えてほしい野菜と言えるでしょう。
チャーシュー

具の中でも花形的存在であるチャーシュー。かつては、その厚みや枚数の多い少ないがラーメン店選びの基準になるなることも多かった。現在でもラーメンの具の中では、ダントツの人気をもっていると言って過言ではない。
ところでこのチャーシュー、漢字では、「叉焼」と書く。「叉焼」は、本来、中国に古くから伝わる豚肉調理法のひとつで下味をつけた脂身の少ない豚のもも肉を紅糟(ホンサオ)とよばれる赤いタレをたっぷりとかけ、焼釜と呼ばれる特製の釜で、じっくり焼いたもの。なおこれと似た方法が「焼豚」と呼ばれる調理方法、これも「叉焼」と同様、専用の炉で焼くのだが、「叉焼」との大きな違いは、豚の三枚肉を使い、紅糟(ホンサオ)でなく、塩やコショウをすり込む方法。脂身がついているので、「叉焼」よりは脂っこいのが特徴だ。
しかし現在、前述の「叉焼」、「焼豚」といった調理方法でチャーシューをつくるラーメン店はほとんどないのが現状だ。その多くは、豚のバラ肉、もも肉、肩ロースをたこ糸で縛り、塩、コショウで下味をつけた醤油ベースのタレでグツグツと煮こむという方法がとられるからだ。この調理方法は、「叉焼」や「焼豚」のように“焼く”のではなく“煮る”方法、つまり「煮豚」という調理方法。我々は、この煮豚をチャーシューと呼んで食べているわけなのです。
なお札幌味噌ラーメンにおいては、チャーシューではなく、挽肉を使うお店も多くあります。味噌と挽肉の組み合わせは意外なほどマッチします。ちなみに味噌ラーメンの元祖「味の三平」では、この挽肉がチャーシューの代わりに使われています。
さて、最後にチャーシューで使用する食肉の部位の特徴を簡単に述べます。
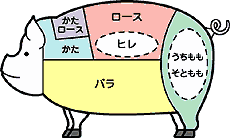
-
かたロース
煮崩れしやすく、味がしみこみにくいため、仕込みが難しい。出来あがりは、口あたりが良くやわらかい。
-
そともも
味がしみこみやすく煮崩れしにくい。出来あがりは、比較的固めとなる。
-
うちもも
かたロースとそとももとの中間的素材で味が比較的しみこみやすく煮崩れしにくい。出来あがりは、かたロースほどではないがやわらかい。
-
バラ
赤肉と脂肪が層になっているが煮崩れはしにくい。脂身を外側になるように巻いてつくる。出来あがりは、とろけるような口あたりが特徴。
めんま

ラーメンの具として欠くことのできないものともいえる「メンマ」。
「メンマ」は、中国でとれる「麻竹」(マチク)という竹の一種(台湾では、、笋干(スンガン)と呼ばれる)を原料に作られます。もともと台湾と中国は、竹の一大産地、200〜300種類の竹が生息しており、「麻竹」もその中のひとつ、ちなみに日本で一般的に食べられるタケノコは、「孟宗竹」(モウソウチク)という種類になります。
さて明治時代、ラーメンの生誕地横浜南京街に住む中国人の多くは、中国福建省、広東省の出身者でした。これらの地方では、前述の「麻竹」が多く自生し、これを豚肉と一緒に煮て、肉のうまみを染みこませて食べるポピュラーな家庭料理が普及していました。これをラーメンの中に入れてみたところ大変好評だったため、その後、具として一般的に使われるようになっていったようです。
このように日本では、ラーメンの創世記から具として親しまれているメンマ、では具体的にどのようにして作られるのでしょうか?まず「麻竹」の伐採のしかたですが、日本のタケノコのように、地中にあるものを掘り返すということはせず、長さ60〜70センチ、直径15センチほどに生長した「麻竹」を刈り取り、皮をむいて、先端と底の部分を切り落とし残った中心部分を加工工場で細かく裁断し、1時間ほど煮込みます。つぎに、かごに入れて、1ヶ月間、土中に埋めて自然発酵させます。十分に発酵が進んで飴色になった麻竹は、かごからとりだされて、天日干しにし、さらに、塩水に漬けてからもう一度、天日干しにし、さらに工場のなかで風圧によって乾燥させます。日本には、こうしてつくられた乾燥メンマが主に輸入されるわけです。
現在、ラーメン店では、この乾燥メンマを塩浸けにしたものを輸入業者などから購入し、店独自の味付けをして使用するのがもっとも一般的です。

 製麺へのこだわり
製麺へのこだわり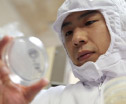 品質・安全への取り組み
品質・安全への取り組み 海外への展開
海外への展開 ご当地ラーメンと札幌ラーメン
ご当地ラーメンと札幌ラーメン 北海道の社長.tvに出演しました。
北海道の社長.tvに出演しました。 テレビ東京の「戦士の逸品」に出演しました。
テレビ東京の「戦士の逸品」に出演しました。 西山社長のフォトギャラリー
西山社長のフォトギャラリー